「HHKB Professional HYBRID Type-S」の長期使用レビュー【無限タイピングしたい方へ】

清水の舞台から飛び降りる覚悟で「HHKB Professional HYBRID Type-S」を購入し、2年が経過しようとしています。
3万円以上する高級機でありながら発売から現在まで今なお根強い人気を誇っているこのキーボード。
どれだけタイピングしても疲労感に襲われないため、普段文書を書く機会が多い方や、プログラマーの方等であれば是非一度チェックしてほしい名器と言えます。
今回は長期間使用してみて再確認したHHKBの魅力についてお伝えしていきます。是非最後までご覧ください。
HHKB Professional HYBRID Type-S の概要
HHKB Professional HYBRID Type-S とは、前モデルの「HHKB Professional 2」や「HHKB Professional BT」からさらに進化を遂げた、革新的なキーボードのこと。
 才川
才川主な特徴は以下のとおりです。
- 静音性の向上:Type-S は、従来の HHKB シリーズに比べてタイピング音が軽減されており、静かな環境での使用に最適。
- ワイヤレス接続:Bluetooth 5.0 を採用し、スマートフォンやタブレットとも接続可能。
- キー配列のカスタマイズ:専用ソフトウェアを利用して、キー配列を自由にカスタマイズ。
こちらの動画でも詳しく解説しています。
デザインと構造について
HHKB Professional HYBRID Type-S のデザインは、シンプルで洗練された印象です。
キーボードのサイズは、幅 294mm × 奥行 110mm × 高さ 39.9mm で、一般的なキーボドに比べてコンパクトな設計となっています。



また重量は約 530g と軽量で、持ち運びにも便利です。
筐体は高品質な PBT (ポリブチレンテレフタラート) 素材を使用し、耐久性に優れています。



キーキャップはダブルショット成形方式で製造されており、文字が消えにくいことも特徴。
細かい部分で耐久力を担保してくれていますね。
購入の動機
なんと言っても「打鍵感」


HHKBの購入に際して、一番の決め手となったのがその打鍵感です。実際に使用してみて、「サクサク」「スコスコ」「トコトコ」を織り交ぜたようななんとも言えない感触の虜になっています。
HHKB Professional HYBRID Type-S は、従来の HHKB シリーズに比べて静音性が大幅に向上しています。



これは、Type-S 専用の静音機構を採用しているため。



静音機構はキースイッチ内部にショック吸収材を使用しキーの上下動の衝撃を緩和することで、タイピング音が軽減されています。
この機能により、オフィスや自宅での作業など静かな環境での使用にも適したものに。
また、HHKB Professional HYBRID Type-S は静電容量無接点方式を搭載しています。
このキースイッチは高い耐久性と快適なタイプ感が特徴で、長時間の入力作業にも疲れにくいと評価されています。
沼への入り口は「G913」
そもそも、この打鍵感を求めるようになった大きな要因は、1年前にロジクールのメカニカルキーボードである「G913」を購入して使用したところまで遡ります。
「G913」にはこれまで使用してきたキーボード達では再現できない心地よい「カチャカチャ感」があり、それがなんともいえずクセになりました。



その頃は「茶軸」を使用していました
キーボードの種類を調べ始めるように


- メンブレン式
-
1,000円〜5,000円くらいの普及価格帯に多いのがこのタイプ。キートップの下にラバーがあり、キーストロークが長めに設計されている。打鍵感は「モニュモニュ」と言った感じ。
- パンタグラフ式
-
ノートPCや薄型キーボードに採用されている事が多いのがこのタイプ。タイピング時の底打ち感を一番感じ易く、音も発生し易い。打鍵感は「パチパチ」と言った感じ。
- メカニカル式
-
キートップの下が金属製のバネや機械式のスイッチで作られており、耐久性に優れたタイプ。もう一つの特徴として、キーの「軸」を選ぶ事ができる。メーカーによって「軸」の種類は様々だが、大きく分けると下記の3種類。
- 「赤軸」(静音製に優れ、押下時の抵抗も少ない。)
- 「青軸」(マウスをクリックした時のような打鍵間。小気味良いタイピングができるものの、キーを押下する度カチカチ音が鳴るので、一人きりの空間での使用が望ましい。)
- 「茶軸」(赤軸と青軸の特徴を織り交ぜたような軸。押下時の程よい感触と、うるさすぎない打鍵音。)
あわせて読みたい
 【Logicool G913 TKL レビュー】薄型・無線で叶える、至高のゲーミング環境。 ロジクールのG913を購入し、毎日使用して1か月程経過しました。 今回はその使用感についてレビューしていきます。 いきなり余談ですが、G913を購入したことで「マウス…
【Logicool G913 TKL レビュー】薄型・無線で叶える、至高のゲーミング環境。 ロジクールのG913を購入し、毎日使用して1か月程経過しました。 今回はその使用感についてレビューしていきます。 いきなり余談ですが、G913を購入したことで「マウス… - 静電容量無接点方式
-
キートップの電極がキーボード本体の(底)電極と接する事なく入力する事ができるため、耐久力が桁違いに高い入力方式。今回紹介している「HHKB」は全てこの方式を採用。底打ち感もないため、一日中タイピングをしてもかなり疲労感を軽減してくれる。


HHKBは静電容量無接点方式
HHKB Professional HYBRID Type-Sを使ってみて
ずっとタイピングしたくなる中毒性



繰り返しになりますが、このキーボードは打鍵感がとにかく最高です。無意味にひたすらタイピングしたくなるような中毒性があります。
そして絶妙な角度、押下厚により、長時間タイピングしたあとでも手や指の疲労感を感じることがありません。
キーボドを置く場所や調整する角度によっても微妙に打鍵感が異なってくるので、自分に合った環境を探し求めるのも一つの楽しみかもしれません。
現在僕が使用しているオススメの組み合わせは、「羊毛マウスパッド」+「ウッドパームレスト」です。見た目も洗礼されている上さらにタイピングが捗り、まさに鬼に金棒の状態。


”墨”の色合いが絶妙


HHKBの色は2色展開となっており、「白」と「墨」が存在します。(以前は期間限定で「雪」が販売されたこともあります。)
”黒”ではなく”墨”という表現に惹かれてしまい、こちらを購入。
まじまじと観察し改めて感じたのですが、色だけでなく、キーボード全体の質感も含めて”墨”なのだなと妙にしっくりきました。
マットな質感が上品
HHKBのキートップはマットな仕上げが施されており、指でなぞるとザラザラした質感が伝わってきます。


以前使用した「G913」や「M1MacBook」はツルツルとしたキートップであるため、これもなかなか新鮮。このマットな加工も”墨”感を上手く演出しているような気がしますね。
タイピング時以外でもなんとなく触りたくなってしまう妙な中毒性も相まって、机に向かうモチベーション維持に一役買ってくれています。
サイズ感も丁度良い感じ
キーボードのサイズは「幅294mm」×「奥行120mm」×「高さ40mm」となっています。
テンキーレスのコンパクトなデザインとなっているため右側にスペースができ、マウス操作に余裕が生まれます。


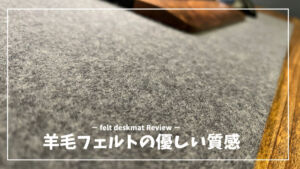
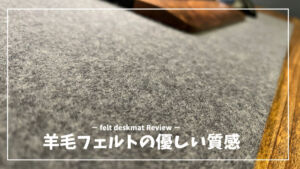


HHKBのタイプは3種類
HHKBは現在「3種類」商品展開されています
- HHKB Professional Classic
-
一番スタンダードなモデル。有線接続(USB typeC)にのみ対応しており、静音機能も無し。少しでもコストを抑えてHHKBの打鍵感を楽しみたいのであればこれ。
- HHKB Professional HYBRID
-
有線接続(USB typeC)と無線接続(Bluetooth)の両方に対応している。静音機能は無し。上記のclassicモデルとは約5,000円程度の価格差。
- HHKB HYBRID Professional HYBRID Type-S
-
有線接続(USB typeC)と無線接続(Bluetooth)の対応に加え、タイピング時の静音機能も付いた最上位モデル。打鍵感、タイピング音ともに楽しみたいならコレ。classicモデルとは約1万円程度の価格差。
| 機種/機能 | typeC接続 | Bluetooth接続 | 静音機能 |
|---|---|---|---|
| Classic | ◯ | × | × |
| HYBRID | ◯ | ◯ | × |
| HYBRID Type-S | ◯ | ◯ | ◯ |


どのモデルも有線接続時は「type-C」
HHKBを有線接続する場合は、どのモデルにおいても「type-C」接続となります。
最近はどのガジェットもほとんどがtype-Cを搭載しているので、ケーブルを共有して使う事ができます。
後述しますが、type-C接続時は「充電」ではなく「給電」であるため、コードを接続している間でのみ使用する事が可能となります。
無線接続時はBluetooth
レスポンスは問題無し
「HYBRID」「HYBRID Type-S」の無線接続はどちらもBluetoothにのみ対応しています。
USBレシーバーによる無線接続に対応していないで、タイピング時の応答速度が気になるところ。ただ、これまで使用する中でレスポンスが気になるようなことはありませんでした。
充電式ではなく乾電池式
HHKBを無線接続する場合、電源は充電式ではなく「乾電池式」となります。
ほとんどのガジェットが軒並み充電式となっている中、この乾電池式に違和感を覚えるかもしれません。
僕も当初は煩わしく感じました。ただ、よく調べてみるとこの方式を採用したのは理由があるようで、乾電池式を採用することでスタミナの劣化を防ぐ事が可能となります。


充電式の場合、繰り返し使用していくことで内蔵バッテリーが劣化しますが、乾電池式であれば常に新しいバッテリーに交換しているようなものなので、常に万全のスタミナで使用し続ける事が可能となります。
HHKBはそもそも本体を超高耐久で使用する事ができる静電容量無接点方式を採用しているため、給電方式においても長期間の使用を見越した乾電池式を採用したのは理にかなっていると言えますね。



公式によれば、単三電池2本で3ヶ月間使用することができるようです。
「英語配列」と「日本語配列」


HHKB Professional HYBRID Type-S は、プログラマーやウェブライターなど、タイピングする機会の多いユーザーに特化したキー配列も特徴の一つ。
従来のキーボードと比較して、Control キーが Caps Lock キーの位置に配置されていたり、Delete キーが Backspace キーと混同していたりと、独自の配列が採用されています。
一見変わった感じの配置に見えますが、慣れてしまえ場プログラミングやテキスト編集作業の効率が向上します。


専用のHHKB キーマップカスタマイズソフトウェアを使用することで、キー配列を自由にカスタマイズすることも可能。
この機能により、従来のキーボードに慣れ親しんだユーザーも自分に合ったキー配列を作成できるため、さらにストレスフリーなタイピングが可能となります。
好みの配置を選べる
HHKBはいずれのモデルでも「英語配列」と「日本語配列(JIS配列)」の2種類からキー配置を選択することが可能です。



僕が購入したのは「日本語配列」モデルです。
キーボード自体のサイズはどちらを選択してもそれほど差がありませんが、英語配列の場合いくつかのキーが排除されています。よりミニマルなものを求めたい方は英語配列を選択してよいかもしれません。
日本語配置を選択した理由
上記で挙げたとおり、英語配列にはいくつか削除されているキーがあり、その中には「矢印キー」も存在しています。
英語配列では「Fn」キーと組み合わせることで足りないキーを補うように設計されているのですが、物理ボタンがないと慣れないうちは苦労しそうです。


矢印キーはExcel以外でも使用する場面が多く、何かと不便になるだろうと思い、日本語配置を選択しました。


HHKB Professional HYBRID Type-Sのメンテナンス


HHKB Professional HYBRID Type-S は、定期的なメンテナンスを行うことでより長く快適に使用する事ができます。



キーボードの寿命を延ばすため、以下の点に注意しましょう。
キーボードの表面
キーボードの表面やキーキャップは、柔らかい布やマイクロファイバークロスを使用して拭くことが推奨されています。
アルコールや強力な洗剤を使用すると、キーボードの表面が傷んだり、キーキャップの文字が消える原因となります。
キーボード内部
キーボード内部のホコリやゴミは定期的にキーボードを裏返しにして、優しくたたくことで取り除くことができます。
また、専用のキーボードクリーナーを使用して、より効果的に清掃できます。
キーキャップ
キーキャップは取り外して洗浄することができます。
ただし、キーキャップを取り外す際には専用のキーキャッププラーを使用し、キースイッチを損傷させないよう注意してください。
Q&A
- HHKBはどのように掃除すべきですか?
-
HHKBの掃除は定期的に行うことが推奨されます。
キーキャップを外し、キーボードの表面や隙間に溜まったホコリを吸い取るために、専用の掃除ブラシや掃除シート、またはキーボードクリーナーを使用しましょう。
キーキャップは水と中性洗剤で洗うことができますが、再度取り付ける際は完全に乾かしてから行うよう注意しましょう。
- HHKBが故障時した場合にはどうすれば?
-
HHKBが故障した場合、まずメーカーのサポートページやマニュアルを参照して対処方法を確認しましょう。
それでも解決しない場合は、購入した販売店やメーカーのサポートセンターに連絡して対応を依頼してください。
- HHKBを購入する際は、どのモデルを選ぶべきでしょうか
-
HHKBモデルの選び方は、用途や好みによって異なります。
例えば、静かな環境での使用を重視する場合は今回ご紹介した「type-S」モデルがおすすめです。
持ち運びだけを考慮するなら、軽量でコンパクトな無線モデルが適しています。
- HHKBはどのモデルも非常に高価ですが、その価値はあるのでしょうか
-
HHKBは高品質な素材と独自の技術により、優れた耐久性と快適なタイピング体験を提供します。
価格に見合った性能が得られるため、長期的な使用を考慮すればその価値は十分にあると言えます。
- HHKBのキーキャップは交換可能ですか?
-
はい、HHKBのキーキャップは交換可能です。
メーカー純正のキーキャップや、一部の互換性のあるサードパーティ製のキーキャップを選ぶことができます。
キーキャップを交換することで、個性的なデザインや異なる素材感を楽しむことができます。
ただし、購入前には商品レビューなどを参照し、互換性を確認してから購入しましょう。
- HHKBのキー配置をカスタマイズする方法は?
-
HHKBのキー配置は、専用ソフトウェアを利用してカスタマイズすることができます。
メーカーのウェブサイトからダウンロードできるソフトウェアをインストールし、好みのキー配置に変更して保存することで、より使いやすいキーボード環境を構築できます。
ただし、ソフトウェアは使用するOSに対応したものを選択する必要があるため注意してください。
まとめ
以上、今回は「HHKB Professional HYBRID Type-S」の特徴、使用感などについてお伝えいたしました。
今回ご紹介したHHKB Professional HYBRID Type-Sは、高い静音性、快適なタイプ感、カスタマイズ性、ワイヤレス接続など、数多くの優れた機能を備えたキーボードです。



特に、プログラマーやエンジニアなどの専門職におすすめできる製品ですが、一般ユーザーにも十分に魅力的なキーボードだと言えるでしょう。
価格はやや高めですが、その性能と品質を考慮すれば十分に納得できるレベルです。
独自のキー配列に慣れるまでの短い期間を乗り越えれば、長期的に見てストレスフリーでタイピング環境を実現できます。
これまでHHKBシリーズを使ったことがない方にも、ぜひ一度試していただきたい逸品となっていますので、気になった方は是非一度チェックしてみてください。






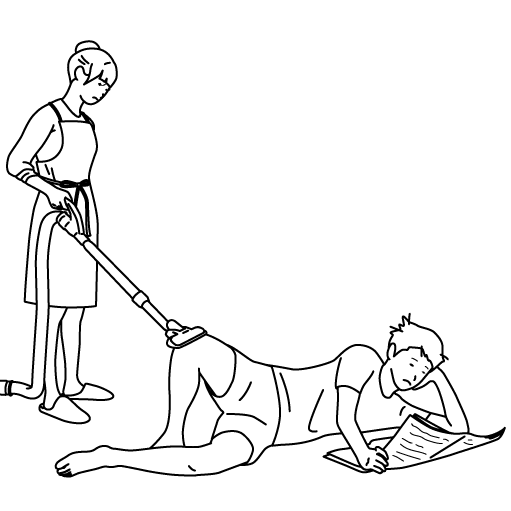
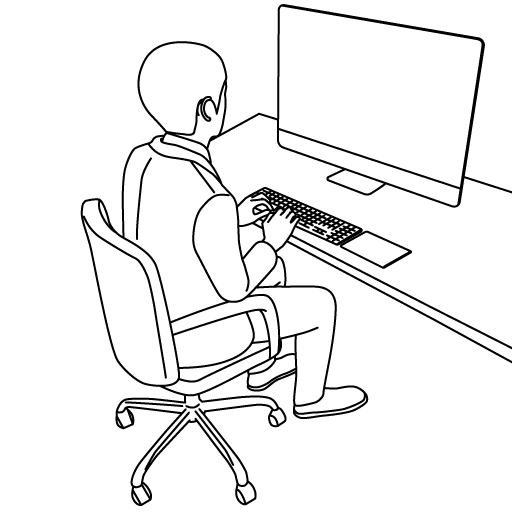
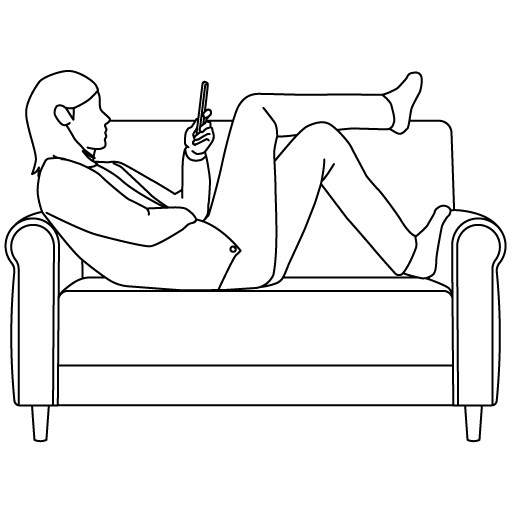

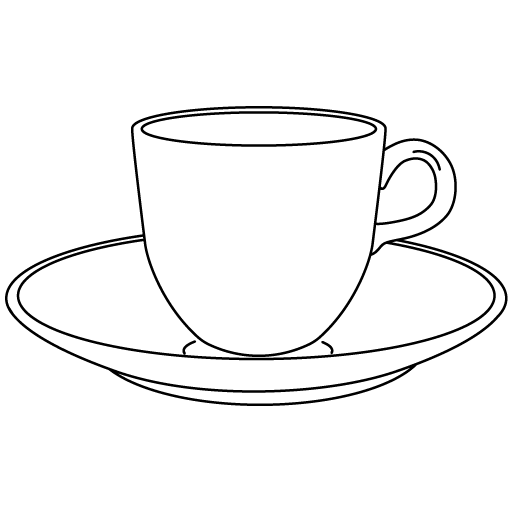
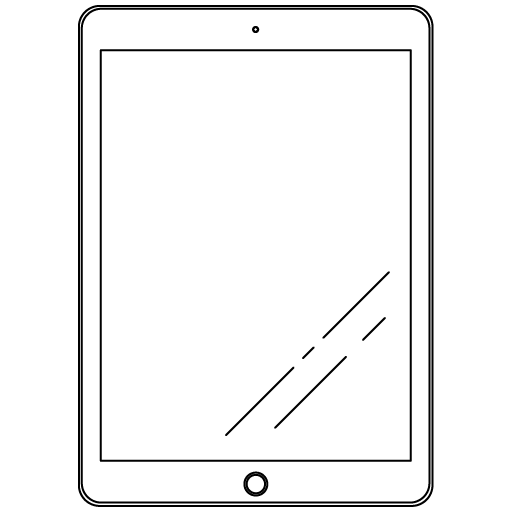
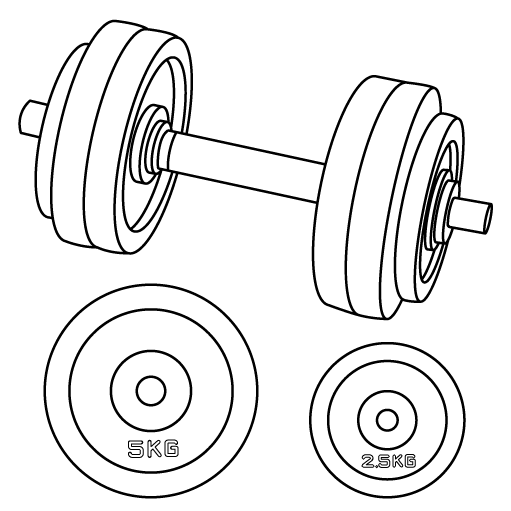
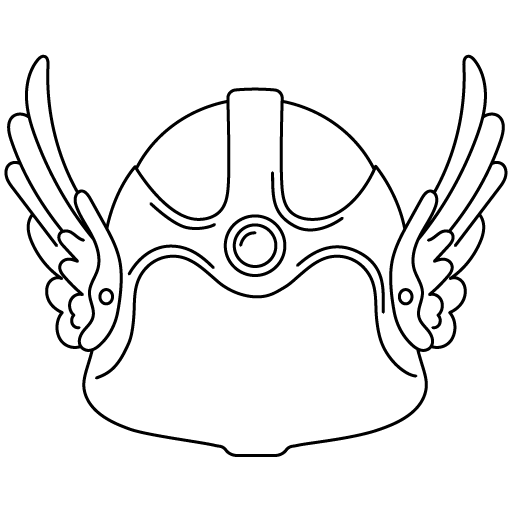
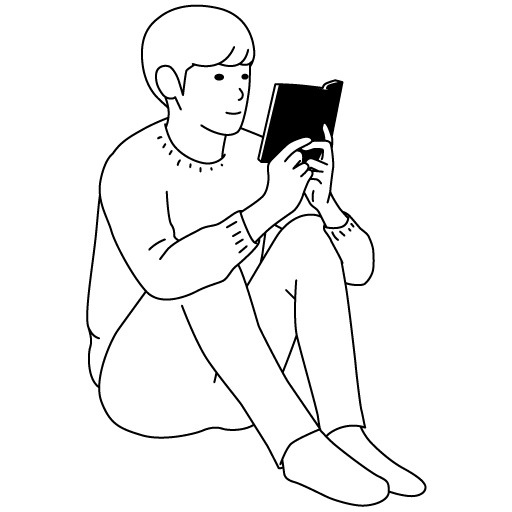
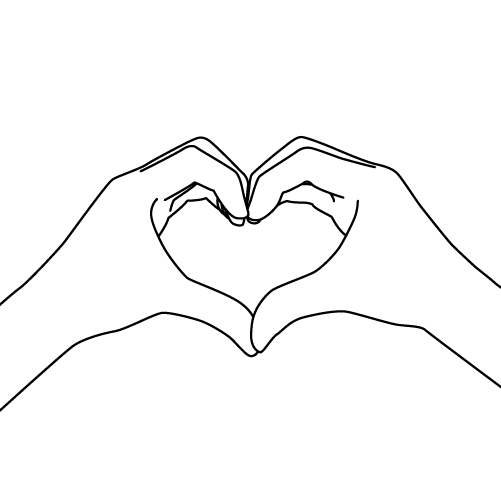




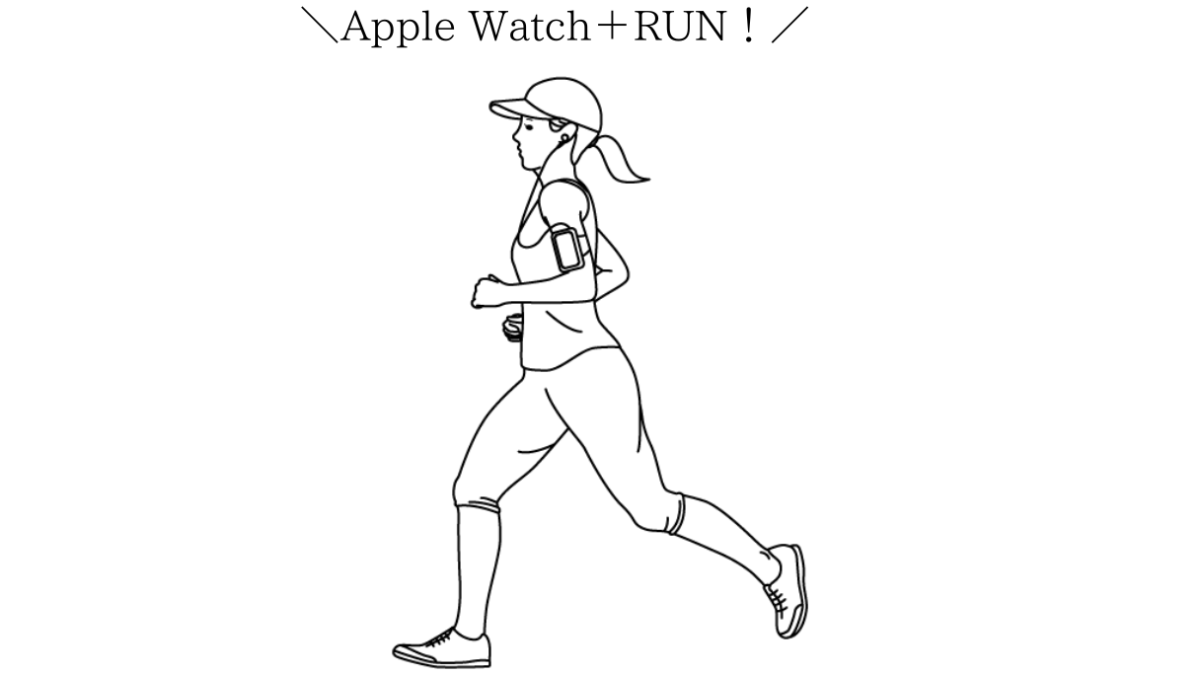

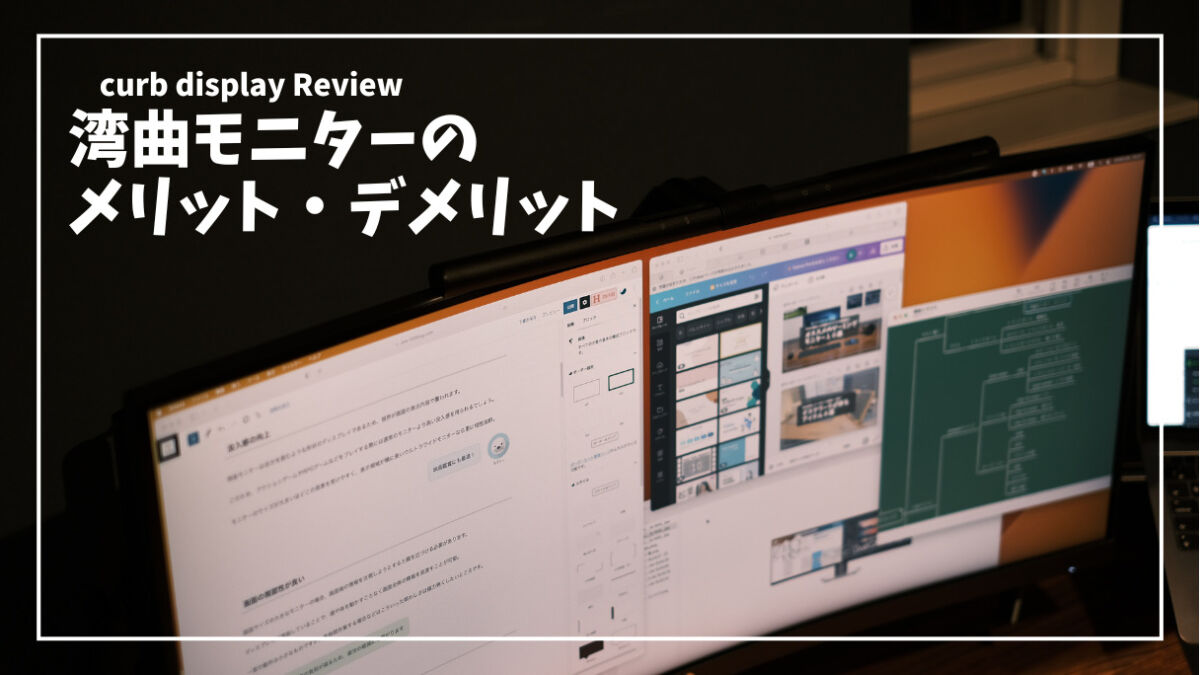

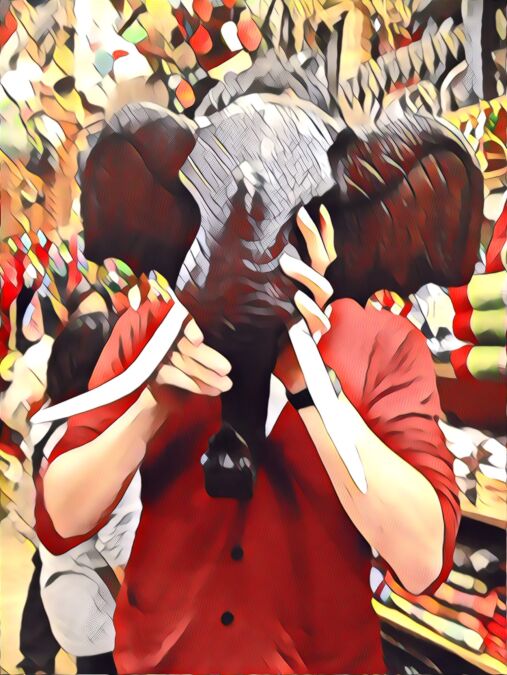


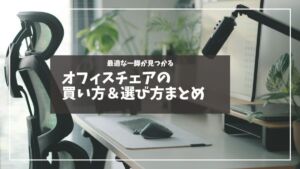
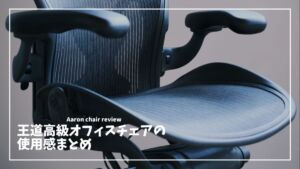
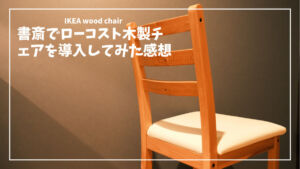
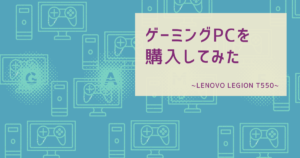
コメント